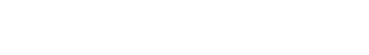デビュー以降、ロック・バンドの可能性をアップデートし続けているレディオヘッド。フィル・セルウェイ(Dr)とともにその屋台骨を支え続けているのがコリン・グリーンウッドである。中心人物であるトム・ヨーク(Vo,Gu)を始めとするメンバー全員がマルチ・ミュージシャンであり、コリンもエレキ・ベース&ウッド・ベース、そしてシンセ・ベースの他にキーボード、サンプラー、パーカッションなどでサウンドに幅と奥行きをもたらしている。同じくレディオヘッドのメンバーであり、現代最高峰とも言える天才ギタリスト、ジョニー・グリーンウッド(Gu)は実弟である。
【本名】コリン・チャールズ・グリーンウッド
【生年月日】1969年6月26日
【出身地】イングランド オックスフォード
【使用ベース】 : Fender Precision Bass、Fender Jazz Bass、Musicman Sterling
【所属バンド】 : レディオヘッド
92年に1stアルバム「パブロ・ハニー」でデビューしたレディオヘッド。以降のアルバムに比べるとUKギター・ロック然とした印象の強いアルバムであるが、トム・ヨークの非凡なメロディ・センスとバンドの陰鬱としたメランコリックな世界観は既にこの時点で完成していたと言える。特筆すべきは、言うまでもなく世界的ヒットとなった「クリープ」。美しいアルペジオとヴォーカル、コーラス部分に鳴り響く轟音ギター、そのバックで淡々とキックにユニゾンするコリンのプレイは、シンプルかつ最大限に曲を引き立てている。
「エニワン・キャン・プレイ・ギター」におけるテヌート&スタッカートを効かせたメイン・リフからなだれ込むコーラス部分のヴォーカルと寄り添うようなベース、「プルーヴ・ユアセルフ」のAメロのヴォーカルに対するカウンター・メロディなど、このアルバムにおけるコリンのプレイはギター・ロックにおける歌伴のお手本となるプレイに溢れている。
95年、2ndアルバムとなる「ザ・ベンズ」を発表。基本的には「パブロ・ハニー」の流れを組むギター・ロックであるが、曲のスケールはより壮大になり、サウンド・プロダクションも豪華になっている。冒頭を飾る「プラネット・テレックス」でのうねるようなグルーヴや、「ハイ・アンド・ドライ」での少ない音数で聴かせるメロディアスなプレイ、「マイ・アイアン・ラング」での無機質かつクールなラインから一変してアグレッシヴになるコーラス部分など、テクニック的に派手さはないもののセンス抜群のプレイを聴かせている。アルバムとしてもこの「ザ・ベンズ」を一番の名盤に挙げるファンも少なくない。
97年に発表され、ロックの歴史を塗り替えた3rd「OKコンピューター」。「エアバック」のおけるベース・ラインの差し込み方、ドラムとの絡みはそれまでのロック・ベースの在り方と一線を画したものとなっており、まるで機械のようなフレージングを生み出している。
その一方「カーマ・ポリス」で聴かせる、シンプルでメロディアスなアプローチも健在。「エレクショネアリング」での歌い上げるようなラインで曲をグルーヴさせる手腕にも脱帽。また、6分を超える大曲「パラノイド・アンドロイド」はロック史に残る名曲。未聴の方は是非一聴を。
Radiohead – Paranoid Android
レディオヘッドがロック・バンドという殻を脱ぎ捨て、エレクトロ・ミュージックとの融合を図っていった2作が00年発表の「キッドA」、そして01年発表の「アムニージアック」である。これらはバンドというアイデンティティを解体、そして再構築した作品であり、この2作の登場によってロックにおけるフィジカルとデジタルの境界が無くなったといってもいい。「キッドA」の幕開けとなる「エヴリシング・イン・イッツ・ライト・プレイス」、3曲目の「ナショナル・アンセム」はクラブ・シーンにも受け入れられる高揚感溢れるチューンに仕上がっており、コリンのベースもダンサブルなグルーヴに満ちている。「アムニージアック」収録の「アイ・マイト・ビー・ロング」の呪術的なリフにも注目。
Radiohead – I Might Be Wrong
03年、前2作のエレクトロ路線からロック・バンドへの回帰を果たした「ヘイル・トゥ・ザ・シーフ」を発表。1曲目の「2+2=5」における躍動感に満ちたギター・ロックは初期のファンを狂喜させた。とは言え前2作で養われたエレクトロのヴァイヴスも随所に盛り込まれており、「シット・ダウン、スタンド・アップ」「ミクサマトーシス」などは反復するリズム、効果的に差し込まれる電子音によるレディオヘッド流エレクトロ・ミュージックを提示している。ライヴでジョニーとエド・オブライエン(Gu)がパーカッションを叩く「ゼア・ゼア」ではこれぞコリンというべきテヌートを効かせたベース・ラインを披露している。
Radiohead – There, There
事前プロモーションなし、ダウンロードによる販売など、その音楽性のみならず、バンドの運営の在り方すら従来の方法論に捕われないというアーティストとしての革新性を示した世界中を驚かせた「イン・レインボウズ」、そして続く「キング・オブ・リムズ」とリリースを重ねるごとにサウンドがソリッドになり、一聴するとシンプルな音像でありながら緻密に計算された音の配置で凄まじい完成度を誇る傑作を生み出し続けている。「キング・オブ・リムズ」収録の「ロータス・フラワー」のグルーヴの生み出し方は秀逸。
Behind the Scenes: Radiohead “Lotus Flower”
堅実なプレイでバンドのボトムを支えるのが、コリンのベースの一番の特徴といえるだろう。これはドラムのフィル・セルウェイのプレイスタイルにもいえることで、ライブでは2人がアイコンタクトを交わしている場面がしばしば見られる。ボトムに徹するといってもいわゆるルート弾きのようなフレーズだけではなく、シンプルながらも印象的でこのベースラインがなければ楽曲の印象がガラッと変わってしまうと思えるベースラインも数多い。さらに、時折聴かれるメロディアスなフレーズも印象的で、押し引きのバランス感覚に優れたクレバーなプレーヤーである。また、クラブミュージックやエレクトロニカなど多彩な要素を持つレディオ・ヘッドの楽曲に、エレキベースやウッドベース、シンセベースなどを用いて的確にアプローチしていく懐の深さも持っている。
近年ではファッションショーのランウェイでベースのソロプレイを披露したり、映画「ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男」の音楽を担当するなど、レディオ・ヘッドのベーシスト以外の活動も多くなっている。
Radiohead – Bloom (live From the Basement)
プレシジョンベースによる太い音色のベースラインが、まるでシンセベースのようだ。間奏ではベースがホーンとともにメロディを演奏している。
あまりにも音楽性の幅が広いレディオヘッドの楽曲を再現するため、ライヴでは前述のとおりキーボードやサンプラーなどもプレイする。
レディオヘッドの名盤を選ぶとしたら「ザ・ベンズ」「OKコンピューター」など、傑作と呼べる作品が多すぎて迷ってしまうところではあるが、ベーシスト的観点からセレクトするならこの「キッドA」を挙げたい。クラブ・チューンへの肉体的アプローチ、シンセ・ベースによるグルーヴなど、普通にプレイしているだけでは思いつかないようなアイデアの宝庫。前述した「エヴリシング・イン・イッツ・ライト・プレイス」「ナショナル・アンセム」でのプレイはもちろんだが、タイトル曲「キッドA」の静なるカオスとでも呼べるトラックの中で存在感を放つベース・ラインが素晴らしい。